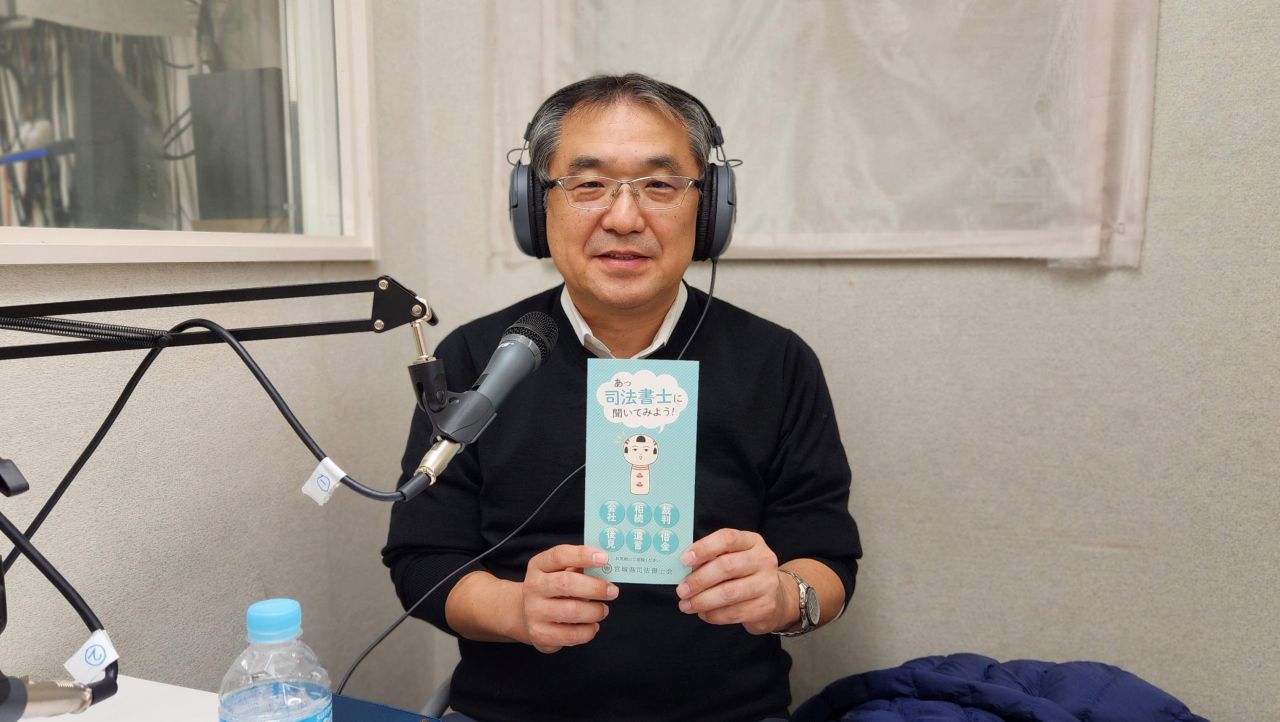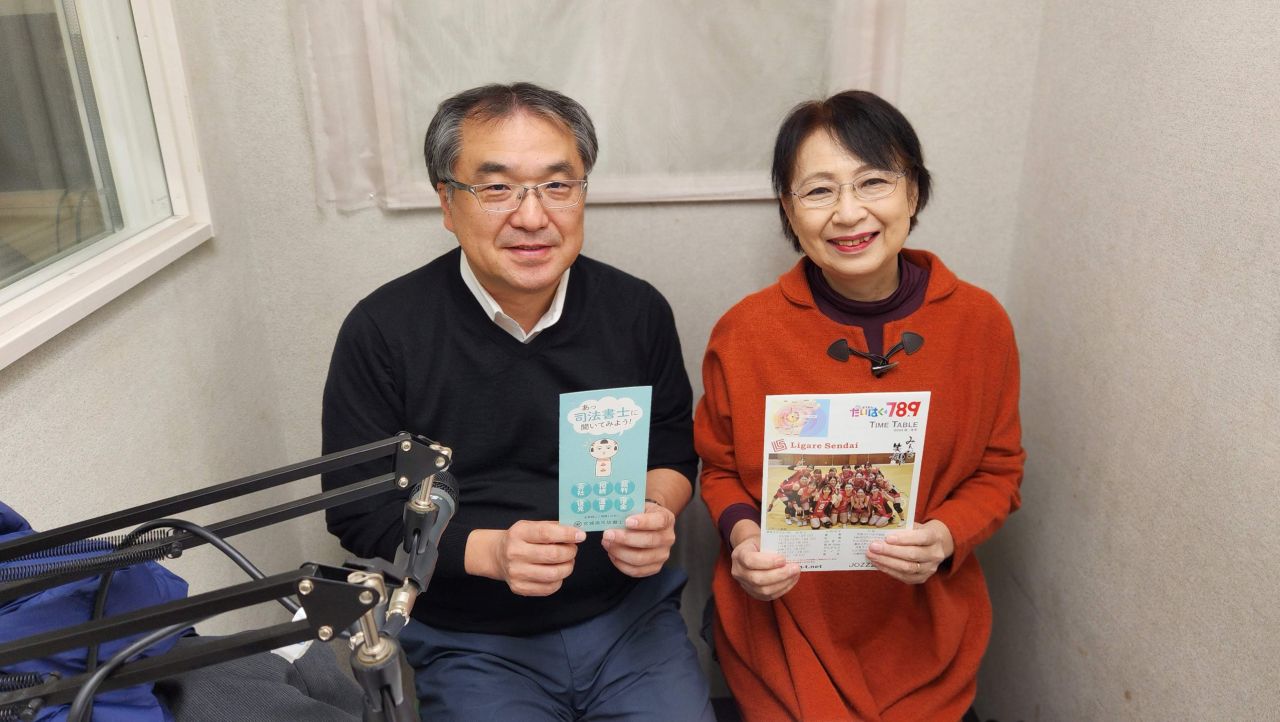【2024.12月】もうすぐお正月。相続について家族で話しましょう(伊藤孝紀会員)
『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。
2024年月12月26日㈭は、宮城県司法書士会の伊藤孝紀(いとう こうき)さんが、「相続について家族で話しましょう」というテーマでお話してくださいました。
相続登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半のお話 皆が集まるお正月は相続の話し合いをするいい機会です
ー 「今回は相続について家族で話しましょう」というテーマですがどんな切り口ですか?
 伊藤 今回はですね、最近こちらのラジオでもいっぱい相続の話ってされてると思うんですけれども、相続登記が今年の4月から義務化になりまして、そして初めてのお正月を迎えます。
伊藤 今回はですね、最近こちらのラジオでもいっぱい相続の話ってされてると思うんですけれども、相続登記が今年の4月から義務化になりまして、そして初めてのお正月を迎えます。
そこで親戚一同が集まったり、家族で集まったりもしますので、もう一度、ちょっと相続のことについてお話しされてみてはいかがでしょうか?ということで、この話をさせていただきたいと思います。
ー 家族での話し合いは大事ですが、話題に出しづらいテーマでは?
 伊藤 遺言の場合は確かに、皆さんから言い出しにくいというお話を聞きますが、相続の場合は亡くなったという事実が直近にあればどうしても迫ってくるものなので、誰かが主導して話を進めればよろしいのかなとは思います。
伊藤 遺言の場合は確かに、皆さんから言い出しにくいというお話を聞きますが、相続の場合は亡くなったという事実が直近にあればどうしても迫ってくるものなので、誰かが主導して話を進めればよろしいのかなとは思います。
ー そういうことなんですね。何か注意点はありますか?
 伊藤 そうですね。今回登記が義務化になってるということの関連で言いますと、例えばお正月に話し合いの中で「この不動産は昔からの流れで、私が長男なので私が全部相続しますね」ということで、皆さんも「そうだね」といってくれてすぐまとまったとします。
伊藤 そうですね。今回登記が義務化になってるということの関連で言いますと、例えばお正月に話し合いの中で「この不動産は昔からの流れで、私が長男なので私が全部相続しますね」ということで、皆さんも「そうだね」といってくれてすぐまとまったとします。
そして皆さんの同意が得られたので、安心してそのまま何もせずにずっと放置しておくという場合も今まではあったと思うんですね。
ですがそのまま時間が経ってしまうと・・・これは実際に私が経験したことですが、10年ぐらい経過してから登記をしたいと思い、関係者にハンコを押してほしいとお願いするわけですが、皆さん、その時はいいと言ったけれども、その時のご自身の経済状況とか、配偶者の方から「どうして権利があるのに」みたいなお話が出て反対されたり、結局その時にやっておけばスムーズにできたものが、あとになるといろいろ揉めたりすることが実際にあるんです。
ですから、法律で3年以内の登記が義務化※されたこともありますし、決まったらすぐに届けるのがよろしいかと思います。お正月は皆さんが集まるのでお話をするいい機会ではないでしょうか。
ー 逆に、その場でもめてしまったら?
 伊藤 そどうしても話し合いがつかない時には、裁判所の遺産分割調停を利用したりそれでもやっぱり駄目という時には、弁護士さんに依頼して、色々間に入ってもらってやるしかないかもしれません。
伊藤 そどうしても話し合いがつかない時には、裁判所の遺産分割調停を利用したりそれでもやっぱり駄目という時には、弁護士さんに依頼して、色々間に入ってもらってやるしかないかもしれません。
司法書士は間に入って調整などを行うことができないので、やはり弁護士さんですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは07:20前後からです。)
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。![]()
![]()
![]()
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
※相続登記は令和6年4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に申請することが義務付けられました。
後半のお話 この機会に登記がされていない土地等について話し合ってみては?
ー 相続の話がまとまらない状態のままずっと放置されるとどうなりますか?
 伊藤 今年の4月に法律が改正される前は、話し合いがまとまらないときに、当分そのままにしておこうということになってそのままにしていても(もちろん早めに済ませたほうがいいのですが)、法律上の違反にはなりませんでした。けれど義務化以降は、まとまらないときでもとりあえずしなければいけない登記がありまして、それが相続人申告登記というものになります。
伊藤 今年の4月に法律が改正される前は、話し合いがまとまらないときに、当分そのままにしておこうということになってそのままにしていても(もちろん早めに済ませたほうがいいのですが)、法律上の違反にはなりませんでした。けれど義務化以降は、まとまらないときでもとりあえずしなければいけない登記がありまして、それが相続人申告登記というものになります。
ー 相続人申告登記は本物の登記とは別のものですか?
 伊藤 本物の登記とは違う別のものです。そちらを相続をした日から3年以内にしておけば、はい、先ほど言った過料(俗に罰金)というものはないということになります。
伊藤 本物の登記とは違う別のものです。そちらを相続をした日から3年以内にしておけば、はい、先ほど言った過料(俗に罰金)というものはないということになります。
相続登記の義務化というのは、ずっと登記を放置しておくと、誰が所有者なのか全く分からない状態になってしまうことを防ぐ意味合いがありますので、少なくとも今、どなたか一人でも相続人が登記簿上でわかるということにしておくということが重要なんじゃないかなと思っています。(要は連絡先ということですね?)それもあると思います。
ー 当然ですが、相続人申告登記をしたままの放置もいけないんですよね?
 伊藤 女そうですね。結局その後にまた遺産分割をどうするかという話し合いをしていただいて、遺産分割で結局話し合いがまとまれば、そこからまた3年以内にちゃんとどなたが名義人になったのかという登記をしなければいけないということになります。
伊藤 女そうですね。結局その後にまた遺産分割をどうするかという話し合いをしていただいて、遺産分割で結局話し合いがまとまれば、そこからまた3年以内にちゃんとどなたが名義人になったのかという登記をしなければいけないということになります。
ー つまり相続人申告登記の後に今度は本当の登記をするわけですね
 伊藤 そうですね、皆さんで話し合いがまとまって、じゃあこれは誰々さんが名義人を受け継ごうとか、これを誰々さんと誰々さんが2分の1ずつ受け継ごうというのが決まったら、そこから3年以内に今の本当の・・・本当のという言い方がいいのかわからないですが、そちらを申請するということになります。
伊藤 そうですね、皆さんで話し合いがまとまって、じゃあこれは誰々さんが名義人を受け継ごうとか、これを誰々さんと誰々さんが2分の1ずつ受け継ごうというのが決まったら、そこから3年以内に今の本当の・・・本当のという言い方がいいのかわからないですが、そちらを申請するということになります。
そういった話し合いをするために、わざわざ電話して集まるのも大変なので、お正月のように皆さんが集まった時をきっかけにして話し合っていただければいいんじゃないかなと思います。
例えばおじいちゃんとかでもいいんですけど、ずっと放置してる登記があったとして、それを皆が集まった時に「実はもう10年くらい前から放っておいている」と切り出すとか、そういうのがわかれば「これを何とかしようよ」みたいな話し合いをしてもいいのかなと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:10から。このお話の続きは16:25前後からです。 )
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。![]()
![]()
![]()
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲
本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲は 近藤真彦 の『ギンギラギンにさりげなく』でした。
伊藤さんのコメント 「単純に元気が出るので。今は持っていないんですけど、少し前にCDを持っていた時に、なんとなく気が乗らない仕事の時とか、そういうのをかけると元気が出てたんです。それと大学生の時にパブでアルバイトをしていて、その時にカラオケのステージがあって、たまにちょっと真似して歌ったりすると、結構皆さん喜んでくれたので、何となく定番で歌っていたという感じですね。」
パーソナリティから 〜必要があってもなくても一度家族で話し合うのが大事~
「お正月に相続について家族で話す」という今回のテーマをお聞きしたとき、相続は人が亡くなった時に発生するものというイメージが強かった私は、新年を祝う行事である「お正月」という言葉に違和感を感じてしまったのですが、それは私の理解不足によるものでした。
司法書士の皆さんがおっしゃる相続は、「相続登記」を指していることが多く、祖父母やご両親が亡くなってもその方たちが所有していた不動産に対して公的な手続きが何もされずに放置されているケースが多くあるようです。
今まではそれでも法律違反にはならなかったのですが、今年の4月の法改正により相続登記が義務化されました。
そこでそういった名義変更が行われていない土地・建物の存在を親族間で共有し、皆が集まるお正月という期間を利用してもう一度話し合ってみませんか?というのが今回の伊藤さんのご提案でした。
本日の放送に限らず、司法書士の皆さんからは、東日本大震災のときに市町村が道路や住宅をつくりたくても、対象となる土地の持ち主がわからずそれが復興の大きな障害になったと聞いています。
そこに今まで住んでいた方が自分の土地だと思っていても、登記上は先代や先々代の持ち物とされているケースがたくさんあり(中にはご親族の誰もがご存じない明治時代の方が所有者だったことも)、法的な相続人をすべて探し出して、相続登記を完了させたうえで交渉を行わないと、一歩も前に進めなかったのです。
今年の法改正はそういった背景をベースに施行されたようですが、私たちにとって相続は一生に一度あるかないかの出来事であり、そもそもの意識がまだ希薄かもしれません。
ちなみに伊藤さんのお話によると、最近は相続登記を依頼されるお客様のタイミングがどんどん早くなっており、ご家族が亡くなってから一週間ぐらいで相談に来られる方もいらっしゃるそうです。(前回ご出演の佐々城翠さんも同じお話をされていました)
誰がどう引き継ぐか?という話し合いが今すぐ必要でない方であっても、こういった話題について家族で気軽に話し合うことが、今後のスムーズな相続登記につながっていくのだと感じました。
*記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン)
お問い合わせ先
※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ)
022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。